2015年の科学
ウィキペディアから
できごと
1月

- 1月6日 – NASAがケプラー宇宙望遠鏡による観測で、これまでに累計で1000個の太陽系外惑星の存在を確認したと発表した[3]。
- 1月7日 – バーモント大学の研究によって、人類は森林伐採や農業などによって、自然の100倍の速さで土壌を侵食させていることが明らかになった[4]。
- 1月13日 – デューク大学での研究で、人の筋肉が実験室で初めて成長させることに成功したと発表された[5]。
- 1月16日 – 2003年から火星で行方が分からなくなっていたビーグル2号を、マーズ・リコネッサンス・オービターから撮影したイシディス平原の高解像度画像から発見したとNASAが発表した[6]。
- 1月26日 – アルカリ金属と水が接触すると爆発するのは、従来考えられていたような単に水素ガスの発生とその発火によるものではなく、水と金属との界面におけるクーロン爆発が反応を促進させるためであることが明らかになった[7][8]。
- 1月27日 – NASAのケプラー宇宙望遠鏡が、およそ112億年前に形成されたとされる年老いた恒星ケプラー444の周りを公転する5つの岩石質の太陽系外惑星の存在を確認したと発表された[9]。
- 1月28日 – ペンシルベニア州立大学の研究で、緑茶に含まれる成分である没食子酸エピガロカテキンが口腔がんの予防につながる可能性があると発表された[10]。
2月
- 2月2日 – 北京大学などの研究で、五員環から構成されるペンタグラフェン構造について、理論計算により安定であることが示された[11][12]。
- 2月3日 – アメリカ食品医薬品局(FDA)が進行性乳がんの治療としてパルボシクリブを承認した[13]。
- 2月9日 – ハーバード大学などの研究で、遺伝子操作が加えられたバクテリアと光触媒からイソプロパノールを抽出することに成功し、光合成と同程度の効率を達成したと報告された[14]。
- 2月10日 – NASAが、ハッブル宇宙望遠鏡で撮影された銀河団SDSS J1038+4849と重力レンズを撮影した画像を公開した[15]。

3月
- 3月2日 – 粒子性と波動性の両方の性質を持った状態の光の画像が初めて撮影された[17][18]。
- 3月3日 – NASAのエイムズ研究センターが行った実験で、宇宙空間の条件下、ピリミジンを出発物質としてウラシルやシトシン、チミンといったDNAやRNAを構成する有機化合物を生成させることに成功した[19]。
- 3月5日
- 3月11日 – NASAの探査機カッシーニによる分析で、土星の衛星エンケラドゥスに熱水噴出活動がおきていることを示す証拠が報告された[22]。
- 3月20日 – 2015年3月20日の日食がヨーロッパで観測された。
- 3月24日 – NASAの火星探査車キュリオシティが、火星の地表の堆積物から一酸化窒素を検出した[23]。
- 3月25日 – マサチューセッツ工科大学とベオグラード大学の研究で、3000個の原子を1つの光子を用いて量子もつれの状態にすることに成功し、これまで実験でもつれさせた粒子の数として最大となった[24]。
4月
- 4月1日 – 気候変動の影響でホッキョクグマが陸上で十分な食料を手に入れることができなくなることが明らかとなり、2100年までに絶滅する可能性があることが発表された[25]。
- 4月6日 – ブリティッシュコロンビア大学の研究で、カナダ西部にある氷河が2100年までにその体積の7割を失う可能性が示された[26]。
- 4月14日


5月
- 5月1日 – NASAの水星探査機メッセンジャーが水星に突入し、4年間に渡る軌道上からの観測ミッションを終了した[33]。
- 5月3日 – 当時発見されていた銀河の中では最遠となる、地球からおよそ130億光年離れている銀河EGS-zs8-1が発見されたと発表された[34]。
- 5月6日
- 5月21日 – NASAが、天の川銀河の1万倍ものエネルギーを放出する、既知の銀河の中で最も明るい銀河WISE J224607.57-052635.0の発見を報告した[37]。
- 5月28日 – 国際研究チームがエチオピアで、330万~350万年前の新種の猿人アウストラロピテクス・デイレメダを発見したと『ネイチャー』誌に報告された[38]。
6月
- 6月1日 – これまで古典的なリンパ管システムはないとされてきた脳にもリンパ管が存在していることを発見したと報告された[39]。
- 6月3日 – CERNの大型ハドロン衝突型加速器が、2年間に及んだ修理と改良工事を終了し、運転を再開した。改良によって装置の出力は8兆電子ボルトから13兆電子ボルトまで向上し、より高いエネルギーでの実験が可能となった[40]。
- 6月5日 – NASAの火星探査機マーズ・リコネッサンス・オービターが、火星の南半球にあるアルガ・クレーターにガラスの堆積層(インパクタイト)があることを発見したと公表された[41]。

7月
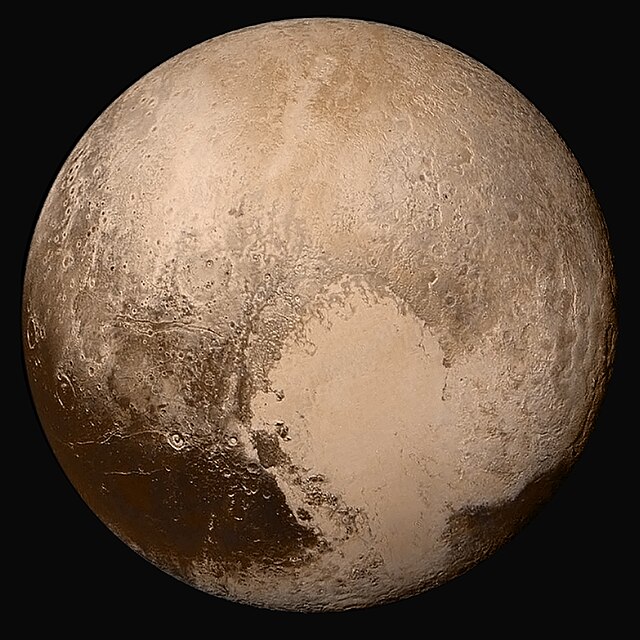
8月
9月
- 9月2日 – 地球上の木の本数を推定する研究で、現在はおよそ3兆本の木が存在するという推定結果が出た[56]。
- 9月3日 – カンザス大学とCERNの大型ハドロン衝突型加速器による研究で、初期宇宙に存在したクォークグルーオンプラズマと呼ばれる状態は、従来考えられていたよりも少ない粒子で生成できることが報告された[57]。
- 9月10日 – 南アフリカで発見された15体分の部分的な骨格の発見について、ヒト族の新種であると報告され、ホモ・ナレディと名付けられた[58]。
- 9月14日 – 重力波検出器LIGOとVirgoの研究チームが、この日に重力波を観測史上初めて検出した[59][60]。発表は翌年2月11日に行われている。
→詳細は「重力波の初検出」を参照

10月
- 10月5日 – 国際自然保護連合(IUCN)の評価によって、サボテンの3分の1近くの種が、違法な取引や他の人類の活動が主な原因で絶滅の危機に瀕していることが明らかとなった[64]。
- 10月6日 – ニューサウスウェールズ大学の研究で、ケイ素からできた初の量子論理ゲートが作成され、2量子ビットの情報の計算を可能にした[65]。
- 10月8日 – NASAの火星探査車キュリオシティによる観測の結果、33~38億年前の火星のゲール・クレーターには湖や河川が存在し、アイオリス山下層に堆積物を供給していたことが確認された[66]。
- 10月20日 – フリンダース大学の研究で、硫黄とリモネンから合成したポリマーが、汚染された水中や土壌中の水銀イオンを効果的に回収できることを発見したと報告された[67]。
- 10月31日 – 大きさがおよそ600m程度の地球近傍小惑星2015 TB145が、月までの距離のおよそ1.266倍まで接近した[68]。
11月

12月
- 12月2日 – コロラド州立大学の研究で、従来の100倍以上の分解能を持つ質量分析イメージング装置によって、細胞組織の3Dマッピングが可能となった[75]。
- 12月3日 – ESAとNASAの宇宙探査機LISA パスファインダーが打ち上げられた[76]。
- 12月4日 – ストックホルム大学の研究で、ダムや灌漑などの施設からの蒸発が人類の淡水消費量を2割近く増加させていることが分かった[77]。
- 12月7日 – 2010年に打ち上げられ、同年に主エンジンの故障によって金星周回軌道の投入に失敗したJAXAの金星探査機あかつきが、この日姿勢制御用エンジンを噴射することで金星周回軌道への投入に成功した[78]。
- 12月9日 – NASAの小惑星探査機ドーンによる観測データから、準惑星ケレスの地表に存在する光点は、硫酸マグネシウム六水和物を含む一種の塩水であることが特定された[79]。
- 12月10日 – 10月に完成したドイツのヴェンデルシュタイン7-X核融合炉で、ヘリウムガスを使用した初のプラズマ実験が行われ、実験運転が開始した[80]。
- 12月18日 – 米科学誌『サイエンス』は今年のブレークスルー・オブ・ザ・イヤー(下記)を発表した[81][82]。
- 12月21日 – スペースX社が使用済みの1段目のファルコン9ロケットを垂直着陸させることに成功した[83]。
受賞
- アーベル賞 – ジョン・ナッシュ、ルイス・ニーレンバーグ
- チューリング賞 – マーティン・ヘルマン、ホイットフィールド・ディフィー
- ラスカー賞
- ガードナー国際賞 – ルイス・カントレー、マイケル・ホール、リン・マクアット、大隅良典、坂口志文
- ウルフ賞
- ウルフ賞物理学部門 – ロバート・キルシュナー、ジェームズ・ビョルケン
- ウルフ賞数学部門 – ジェームズ・アーサー
- ウルフ賞化学部門 – 受賞者なし
- ウルフ賞医学部門 – ジョン・カップラー、フィリッパ・マラック、ジェフリー・ラヴェッチ
- 京都賞
- ショウ賞
- 天文学 – ウィリアム・J・ボラッキー
- 生命科学および医学 – ボニー・バスラー、エヴェレット・ピーター・グリーンバーグ
- 数学 – ゲルト・ファルティングス、Henryk Iwaniec
- トムソン・ロイター引用栄誉賞
- 物理学 – ポール・コーカム、フェレンツ・クラウス、デボラ・S・ジン、王中林
- 化学 – キャロライン・ベルトッツィ、エマニュエル・シャルパンティエ、ジェニファー・ダウドナ、ジョン・グッドイナフ、スタンリー・ウィッティンガム
- 生理学・医学 – 森和俊、ピーター・ウォルター、Alexander Y. Rudensky、坂口志文、Ethan M. Shevach、ジェフリー・ゴードン
- ブレイクスルー賞
- 基礎物理学ブレイクスルー賞 – ソール・パールマッターと超新星宇宙論計画メンバー、ブライアン・P・シュミット、アダム・リースとハイゼット超新星探索チームメンバー
- 生命科学ブレイクスルー賞 – Alim-Louis Benabid、チャールズ・デビッド・アリス、ヴィクター・アンブロス、Gary Ruvkun、ジェニファー・ダウドナ、エマニュエル・シャルパンティエ
- 数学ブレイクスルー賞 – サイモン・ドナルドソン、マキシム・コンツェビッチ、ジェイコブ・ル―リー、テレンス・タオ、リチャード・テイラー
- ノーベル賞
死去
カッコ内は生誕年である。
- 1月9日 – 高瀬文志郎、日本の天文学者(* 1924年)
- 1月27日 – チャールズ・タウンズ、アメリカ合衆国の物理学者、ノーベル物理学賞受賞者(* 1915年)
- 1月28日 – イヴ・ショーヴァン、フランスの化学者、ノーベル化学賞受賞者(* 1930年)
- 2月4日 – 日沼頼夫、日本の医学者、ウイルス学者(* 1925年)
- 2月5日 – ヴァル・フィッチ、アメリカ合衆国の物理学者、ノーベル物理学賞受賞者(* 1923年)
- 2月11日 – 田中健蔵、日本の病理学者(* 1922年)
- 2月16日 – 田中郁三、日本の化学者(* 1926年)
- 3月5日 – 平林眞、日本の金属学者(* 1925年)
- 3月16日 – 田崎明、日本の物理学者(* 1934年)
- 4月22日 – 赤羽賢司、日本の天文学者(* 1926年)
- 4月29日 – ポール・ヒューダック、アメリカ合衆国の計算機科学者(* 1952年)
- 5月15日 – 伊藤嘉昭、日本の生物学者(* 1930年)
- 5月23日 – ジョン・ナッシュ、アメリカ合衆国の数学者、ノーベル経済学賞受賞者、アーベル賞受賞者(* 1928年)
- 6月2日 – アーウィン・ローズ、アメリカ合衆国の生化学者、ノーベル化学賞受賞者(* 1926年)
- 6月5日 – 清水信義、日本の遺伝子学者(* 1941年)
- 7月5日 – 南部陽一郎、日本出身のアメリカ合衆国の理論物理学者、ウルフ賞物理学部門受賞者、ノーベル物理学賞受賞者(* 1921年)
- 8月30日 – オリバー・サックス、イギリスの神経学者(* 1933年)
- 9月19日 – 小畠郁生、日本の古生物学者(* 1929年)
- 12月4日 – 田村三郎、日本の農芸化学者(* 1917年)
- 12月17日 – 早石修、日本の生化学者、ウルフ賞医学部門受賞者(* 1920年)
- 12月23日 – アルフレッド・ギルマン、アメリカ合衆国の科学者、ノーベル生理学・医学賞受賞者(* 1941年)
- 12月28日 – 坂井光夫、日本の物理学者(* 1921年)
脚注
関連項目
外部リンク
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.