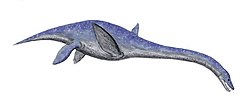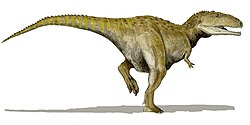トップQs
タイムライン
チャット
視点
チューロニアン
ウィキペディアから
Remove ads
チューロニアン(英語:Turonian)は、9390万年前(誤差80万年)から8980万年前(誤差100万年)にあたる後期白亜紀の地質時代名の一つ[1]。
なお、「チューロン階」「チューロニアン階」という名称があるが、これらは時代を示すものではない。「階」は地層に対して当てられる単位(層序名)であり、層序名「チューロン階」「チューロニアン階」と時代名「チューロン期」「チューロニアン期」は対を成す関係である。詳しくは「累代」を参照のこと。
Remove ads
層序学的定義

チューロニアンはフランスの古生物学者アルシド・ドルビニにより1842年に定義された。彼はフランスのトゥーレーヌ州のトゥールという都市にちなんで命名し、ここを模式地とした。
チューロニアンの最下部はアンモナイトの種である Wutinoceras devonense が地質柱状図に初めて出現する場所と定義されている。チューロニアンの国際標準模式層断面及び地点(GSSP)はアメリカ合衆国コロラド州のプエブロ近辺のロックキャニオン背斜に位置する(38° 16' 56" N, 104° 43' 39" W)[2]。
チューロニアンの最上部(すなわちコニアシアンの最下部)はイノセラムス科の二枚貝である Cremnoceramus rotundatus が地質柱状図に初めて出現する場所と定義されている。
Remove ads
細分化
チューロニアンは前期(下部)・中期(中部)・後期(上部)の亜期(亜階)に区分されることがある。テチス海においては以下のアンモナイトのバイオゾーンが含まれる。
- Subprionocyclus neptuni のゾーン(上部)
- Collignoniceras woollgari のゾーン(中部)
- Mammites nodosoides のゾーン
- Watinoceras coloradoense ないし Watinoceras devonense のゾーン(最後の2つはともに下部)
他の重要な示準化石にはイノセラムス科のイノセラムス3種(I. schloenbachi と I. lamarcki および I. labiatus)がある。イノセラムスは現代のイガイに関連する二枚貝の軟体動物である。
環境
チューロニアンの前の地質時代であるセノマニアンとの境界では海面上昇に伴う世界規模の海洋無酸素事変(OAE 2)が発生した。無酸素事変の中心となったのは大西洋とテチス海であったが、海洋無脊椎動物の絶滅パターンに差はあれど日本近海の生物相も影響を受けた。北海道のアンモナイトは境界から20 - 50万年後に回復を見せた[3]。OAE 2とそれ以降の新種の出現はチューロニアンの基底を定義する。国際地質科学連合の白亜系層序学小委員会では、OAE 2のδ13C値の正シフトの終了がセノマニアン/チューロニアン境界と定義されている[4]。
炭素・酸素同位体比の研究から、後期チューロニアンからコニアシアンにかけて海水準低下と地球規模の気温低下が起きていることが示された。後期白亜紀は全体として寒冷化しており、火山活動で放出された二酸化炭素による温室効果で一時的な温暖化が繰り返されていた[4]。
日本において
北海道では中部蝦夷層群三笠層がセノマニアンから中部チューロニアンに、上部蝦夷層群が上部チューロニアンにあたる[5]。チューロニアン期の間にはニッポニテスなど新たな異常巻きアンモナイトのグループが出現したほか、ユーバリセラス、オビラセラス、シューパロセラスといった肋の発達したアンモナイトが生息した[6]。
主な生物
要約
視点
アンモナイト
日本で産出するアンモナイトを挙げる[7]。
|
|
|
曲竜類
鳥群
角竜類
ワニ形上目
哺乳類
鳥脚類
首長竜類
翼竜
有鱗目
竜脚類
非鳥類型獣脚類
Remove ads
出典
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads