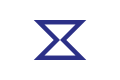トップQs
タイムライン
チャット
視点
市町村旗
市区町村の象徴となる旗 ウィキペディアから
Remove ads
市町村旗(しちょうそんき)は、日本の市町村を象徴する旗である。

沖縄県浦添市にて
概説
市町村において公的行事や公的機関では国旗や都道府県旗などと一緒に市町村旗が掲揚される。
デザインとしては市町村章をそのまま市町村旗の中央に配置するものが多い。配色は都道府県旗に準じる場合が数多くみられ、群馬県旗に対する前橋・高崎・桐生市旗(紫と白の配色)や、神奈川県旗に対する横浜・横須賀・厚木市旗(白と赤の配色)などがあげられる[1]。市町村によっては市町村章とは全く異なるデザインがある(例:兵庫県の姫路市や西宮市、佐賀県の多久市、鹿児島県の鹿屋市など)。
目的
- 豊橋市旗
- 刈羽村旗
旗の使用場所

歴史
市町村旗の一覧
- 北海道地方
- 東北地方
- 関東地方
- 甲信越地方
- 北陸地方
- 東海地方
- 近畿地方
- 中国地方
- 四国地方
- 九州地方
- 沖縄地方
Remove ads
脚注
参考文献
関連項目
外部リンク
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads