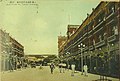ショップハウス
住宅と商店がはいったビル ウィキペディアから
ショップハウス(英語: Shophouse、中国語: 店屋)は、華南および東南アジアに見られる土着建築。多くは2〜3階建てで、1階を店舖として、2、3階を住居として使用する[1][2]。香港では下舖上居(英語意譯:living above store)、台湾では街屋(英語: Townhouse)と呼ばれる[3] [4]。店舖全面には騎楼が設けられ、風通しを良くするとともに雨や直射日光を遮る効果がある[5]。

東南アジアの多くのショップハウスは税制や構造上の規制により細長い設計となっている。また当地の騎楼は法例により幅員を5フィート (1.5 m)と定められており、それゆえに「五脚基」と呼ばれる。
設計と特徵
要約
視点

騎楼
→「騎楼」も参照

1822年、シンガポールの都市計画に関する指示がベンクレーン副総督トーマス・スタンフォード・ラッフルズによって出された。その中で、各住宅は「一定の深さのベランダを設け、常に開放されていること。また、通りの両側に連続した屋根付きの通路(a continued and covered passage)を形成すること」と規定された[6]。この指示により、シンガポールではアーケードやコロネードが連続的な公共通路を形成する、規則的で統一された街並みが生まれた。その後、他の海峡植民地でも「連続した屋根付き通路」として知られる「五脚基(英語: five-foot way)」が義務付けられ、「海峡植民地様式」の建築物の特徴的な要素となった[7][8]。この特徴は19世紀半ば以降、タイやフィリピンなどの東南アジア諸国、さらには一部東アジア諸国にも広がった[8]。
こうした覆い付きの歩道は、華南、台湾、香港で見られる「騎楼」と呼ばれる建物にも見られるが、これはシンガポールのショップハウスの影響を受けて発展した建築様式である[9]。清末の台北、日本統治下の台湾、そして中華民国期の華南では同様の規則が適用され、より広いスペースが義務付けられた[10]。1876年には、香港政庁が賃借人に対して、ベランダ(香港植民地の公道)上に張り出しを建てることを許可した。これにより居住空間を拡張することが可能になったが[11] 、規則的で統一された街並みを作る意図はなかった。
ファサード
建物のファサードや柱には装飾が施されることがある。ファサードの装飾は中国、ヨーロッパ、マレーの伝統から影響を受けているが、ヨーロッパの要素が支配的である[12][13]。ヨーロッパの新古典主義的なモチーフには、エッグ・アンド・ダートや、柱に施されたイオニア式やコリント式の柱頭などがある。ショップハウスの装飾の度合いは、所有者の繁栄やその地域の発展状況に依存し、都市部やかつての新興市街地にあるショップハウスのファサードは、一般的に田舎の質素なショップハウスよりも凝ったものになっている。
1930年代から1950年代にかけては、石造を多用したアール・デコやストリームライン・モダンが主流となった。1950年代から1980年代にかけてのモダンなバリエーションでは装飾が一切なく、国際様式やブルータリズムに触発された、堂々とした幾何学的かつ実用的な形状で設計される傾向があった。1990年代以降、建物はポストモダンや復興主義を採用し始めた[要出典]。
用途
1階部分はほとんどの場合、商業目的に使用され、上層階は住宅として利用される[14]。1階は飲食店、オフィス、商店、または作業場として使用されるが、もし1階に生活空間が含まれる場合(通常は後屋に位置する)、応接室、客室、または先祖の祭壇を備えたフォーマルな居間として使用されることがある[要出典]。定住地が繁栄し、人口が増加するにつれて、一部店舗は診療所、薬局、法律事務所、質屋、旅行代理店などの専門的な用途に使用されるようになった[要出典]。飲食店は通常、リーズナブルな価格で提供される中華風、パダン風(ハラール)、またはシャム風の料理など、さまざまなメニューが扱われる。屋台は店舗のスペースの一部を賃借し、焼きそば、チャーハン、インド風パンケーキ、麺スープなど特定の料理を提供していた。飲み物は別の屋台や時にはショップハウスのオーナー自身が提供した。シンガポールにおいては、このような屋台はホーカーセンターに取って代わられている[要出典]。
通りに面した角地は、飲食店にとって最良の立地として重宝された[要出典]。

- ジャカルタ・草埔(Glodok)の薬局、1991年
分布
要約
視点
シンガポール

シンガポールのショップハウスは、植民地時代の19世紀初頭に発展した。その起源は、トーマス・スタンフォード・ラッフルズがシンガポールの都市計画において建物の統一性と規則性、使用される材料、さらに屋根付き通路といった建物の特徴を明確に規定したことにある[6]。植民地時代の終了後、ショップハウスは老朽化し、一部は放棄されるか、解体作業や、時には火災によって取り壊された[15]。
シンガポールでは、1960年代初頭に制定され、1973年に改正された都市開発のための土地収用法(Land Acquisition Act)がショップハウスの所有者に影響を与え、再開発のためにそのショップハウスが収用される際に重大な補償の不公平をもたらした[16]。数十年にわたり、中心部の歴史的ショップハウスの一画が高密度開発や政府施設の建設のために取り壊された。
マレーシアの植民地時代のショップハウスの所有者と居住者は、1956年から1966年にかけて制定された一連の家賃統制法(Control of Rent Act)に関わる様々な経験を経た[17]。最も最近の1966年の「家賃統制法」の下では、1948年以前に建設された民間所有の建物(多数のショップハウスを含む)が、住宅不足を緩和するために家賃価格統制の対象とされた[18]。この法律は、急速に都市化する人口に十分な手頃な価格の住宅を提供することを目的としていた。1966年の法律導入後の数十年間、ショップハウスが建つ土地の開発は、低い家賃収入のためにしばしば採算が取れず、歴史的な都市地区が停滞する一方で、効果的に保存される結果となった。もっとも、経済成長期には、政府の収用や火災による破壊など、さまざまな理由でショップハウスの一画が取り壊されることもあった。1997年の法律廃止により、土地所有者は家賃を設定する権限を与えられ、1948年以前のショップハウスを開発したり売却したりする動機付けがなされ[18]、その結果、低所得の借主が追い出され、多くの建物が大規模に改築されるか、2000年代から2010年代にかけて再開発のために取り壊された。また、ショップハウスが違法に密閉され、燕の巣の採集用に使用されている事例も記録されており、それによって建物内部に長期的な損傷が生じている[19]。
シンガポールで土地収用法の影響を免れた多くのショップハウスは、現在ある種の復活を遂げており、その中には修復されてバジェットホテル、茶屋、映画館として改装されたものもある。現在では、いくつかのショップハウスは建築的なランドマークと見なされ、その価値は大きく増加している。2011年、シンガポールでは、ショップハウスの3軒に2軒が170万~550万シンガポール・ドル(140万~440万米ドル)の価格で売却され、より大きなユニットは1000万~1250万シンガポール・ドル(800万~1000万米ドル)で売却された。これは2010年からの急激な増加であり、平方フィートあたりの平均価格は2010年から21%上昇した。2011年のシンガポールnおける価格中央値は2007年と比べて74%高くなっている[20]。
- ブギスの陳桂蘭街(Tan Quee Lan Street)にある戦前期のショップハウス
- ブギス・ジャンクションにある戦前期のショップハウスに設置されたガラスの屋根。2019年2月撮影
- シンガポールの五脚基
マレーシア
ジョホール州、クアラルンプール、ヌグリ・スンビラン州、ペラ州、セランゴール州などの開発が進んだ地域では歴史的なショップハウスの保存が大きく損なわれているが、ムラカ州とペナン州のショップハウスでは、両州の歴史的建造物保存運動の影響で、シンガポールと同様の再生が進み、より多くの配慮と注目を受けている(マラッカ市とジョージタウンは2008年にユネスコの世界遺産に登録されている)。しかし、両都市ではジェントリフィケーションが生じており、歴史地区内での賃貸料や不動産購入の高騰のために古くからのショップハウスの借主が追い出されている。2012年には、ジョージタウンで第二次世界大戦前のショップハウスの購入価格が1平方フィートあたり2,000リンギット(660米ドル)に達し、これはクアラルンプール市中心部の最も高価なコンドミニアムユニットと同じ価格に相当する[21]。
- ゲストハウスに改装されたマラッカの文化財ショップハウス、2008年
- ペナン・ジョージタウンの文化財ショップハウス、2008年
- セランゴールのショップハウス
インドネシア
ショップハウスは、オランダ植民地時代から非常に人気があり、特に唐人街(Pecinan)で見られた。伝統的なショップハウスは現在、現代的なものに取って代わられ、これらは「ruko(rumah toko)」と呼ばれている[要出典]。
- ジャカルタ・スネンのJalan Kramat Raya、1991年
- ジャカルタ・スネンの現代的ショップハウス・Ruko、2010年
香港

- 1882年的香港店屋
- 1905年的香港店屋
台湾
→「騎楼」も参照
その他の地区
関連項目
参考文献
外部リンク
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.