オキアミ
軟甲綱真軟甲亜綱ホンエビ上目オキアミ目に属する甲殻類の総称 ウィキペディアから
オキアミ(沖醤蝦、英: krill)は、軟甲綱 真軟甲亜綱 ホンエビ上目 オキアミ目に属する甲殻類の総称。学名から Euphausiids とも呼ばれる[1]。英名の「Krill」はノルウェー語で「稚魚」を意味する[2]。世界中の海洋に生息する小型甲殻類である[3]。形態はエビに似るが、胸肢の付け根に鰓が露出している点でエビ目とは区別できる[4]。プランクトン(浮遊生物)であるが、体長3-6cmなのでプランクトンとしてはかなり大きい。
| オキアミ目 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Northern krill Meganyctiphanes norvegica | |||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 学名 | |||||||||||||||||||||
| Euphausiacea Dana, 1852 | |||||||||||||||||||||
| 英名 | |||||||||||||||||||||
| Krill | |||||||||||||||||||||
| 科 | |||||||||||||||||||||
食物連鎖の底辺に近く、重要な栄養段階を占めると考えられている。植物プランクトンや動物プランクトンを食べ、多くの大型動物の主な食料源でもある。南極海におけるナンキョクオキアミの推定バイオマス量は約3億7900万トンで[5]、総バイオマス量が最も大きい種の1つとなっている。ナンキョクオキアミの半分以上は、毎年クジラ、アザラシ、ペンギン、海鳥、イカ、魚類に食べられている。ほとんどのオキアミは毎日大規模な日周鉛直移動を行い、夜間は海面近くで、日中は深海で生活する。
南極海と日本近海では商業的に漁獲されている。世界全体の漁獲量は年間15万-20万トンで、そのほとんどはスコシア海で漁獲される。漁獲されたオキアミのほとんどは養殖や水族館の餌、スポーツフィッシングの餌、または製薬において使われる。日本で販売されているのは、三陸沖などで漁獲されるツノナシオキアミ(イサダ)と、南極海に生息するナンキョクオキアミである。 後者はシロナガスクジラなどヒゲクジラ類の主要な餌料である。オキアミはいくつかの国で食用にもされている。スペインとフィリピンでは camarones として知られている。フィリピンでは alamang とも呼ばれ、バゴーンと呼ばれる塩辛いペーストを作るのに使われている。日本で「アミエビ」の名で塩辛などの食品として売られているものは本種ではなく、より小型の名称の似たエビの一種である「アキアミ」である。
分類
要約
視点
オキアミ目には2科が知られている。オキアミ科には10属に約85種が分類され、オキアミ属には最多の31種が属する[6]。ソコオキアミ科には水深1000m以上の深海に生息するソコオキアミ1種のみが分類され、現存するオキアミの中で最も原始的な種と考えられている[7]。ナンキョクオキアミ、ツノナシオキアミ、Northern krillなどは商業漁業の対象となる[8]。
系統
| オキアミ目の系統分類[9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統分類は形態学に基づき、(♠) はMaas & Waloszek(2001)内で提唱された分類群で[9]、(♣) はネマトブラキオン属と関連する側系統群であり[9]、(♦) はCasanova (1984)とは異なり[10]、カクエリオキアミ属は Nyctiphanes の姉妹群、オキアミ属はチサノポーダ属の姉妹群、ネマトブラキオン属はスティロケイロン属の姉妹群である。 |
オキアミ目は裸出した樹枝状の鰓や細い胸脚など、いくつかの独特な固有派生形質を持つため、単系統群であると考えられており[11]、分子生物学的研究によっても同様の結果が得られている[12][13][14]。
オキアミ目の位置については多くの説がある。1830年にアンリ・ミルヌ=エドワールが初めて Thysanopode tricuspide を記載し、どちらも二枝に分かれた胸脚を持つため、当時の学者はオキアミ目とアミ目を裂脚目 Schizopoda に分類したが、1883年にヨハン・エリック・ヴェスティ・ボアズは裂脚目を2つの目に分割した[15]。1904年にウィリアム・トーマス・カルマンはアミ目をフクロエビ上目、オキアミ目をホンエビ上目に分類したが、1930年代までは裂脚目を認める意見もあった[11]。その後はロバート・ガーニーとイザベラ・ゴードンが指摘したように、発達段階の類似性に基づき、十脚目のクルマエビ科と同じグループに分類されるべきであると提案された[16][17]。オキアミは十脚目とアミ目の形態学的特徴の一部を共有しているため、こうした議論が起こったのである[11]。
分子生物学的研究では、ソコオキアミやアンフィオニデスなど重要な種が少ないためか、明確な分類が出来ていない。ある研究では基底的なアミ目を含むホンエビ上目の単系統性を支持しており[18]、別の研究ではオキアミ目をアミ目と分類し[13]、さらに別の研究ではオキアミ目をトゲエビ亜綱と分類している[19]。
進化
オキアミ目と明確に特定できる化石は現在知られていない。絶滅した真軟甲亜綱の中には、Anthracophausia、現在は奇泳目に分類されている Crangopsis [9]、Palaeomysis など、オキアミ目に分類されてきた属も存在する[20]。種分化の年代は分子時計によって推定されており、オキアミ科の最後の共通祖先は、約1億3千万年前の前期白亜紀に生息していたとされる[13]。
下位分類
主に和名のある種を挙げる。和名と種数は佐々木(2023)を参考[21]。
- オキアミ科 Euphausiidae
- オキアミ属 Euphausia - 34種
- Hansarsia - 7種
- ホソテナガオキアミ Hansarsia tenella
- Meganyctiphanes - 1種
- ネマトブラキオン属 Nematobrachion - 3種
- Nyctiphanes - 4種
- カクエリオキアミ属 Pseudeuphausia - 3種
- カクエリオキアミ Pseudeuphausia latifrons
- スティロケイロン属 Stylocheiron - 12種
- ヒゲブトテナガオキアミ Stylocheiron carinatum
- テッサラブラキオン属 Tessarabrachion - 1種
- チサノエッサ属 Thysanoessa - 10種
- ノコギリテナガオキアミ Thysanoessa gregaria
- トゲホクヨウオキアミ (シャコタンオキアミ) Thysanoessa inermis
- チサノポーダ属 Thysanopoda - 14種
- マルエリオキアミ Thysanopoda obtusifrons
- ミツツノオキアミ Thysanopoda tricuspida
- ソコオキアミ科 Bentheuphausiidae - 1属1種
- ソコオキアミ属 Bentheuphausia
分布
世界中の海域に分布し、多くの種は特定の地域の沿岸の固有種である。ソコオキアミは世界中の深海に分布する汎存種である[22]。チサノエッサ属は大西洋と太平洋に分布する[23]。ツノナシオキアミは太平洋に分布する。Northern krillは地中海から大西洋にかけて分布する。Nyctiphanes 属の4種は沿岸域に分布する[24]。カリフォルニア海流、フンボルト海流、ベンゲラ海流、カナリア海流の湧昇域に非常に豊富である[25][26][27]。コオリオキアミは南極大陸の沿岸に固有である[28]。その他にも Nyctiphanes capensis はベンゲラ海流に[24]、Euphausia mucronata はフンボルト海流に[29]、オキアミ属の6種は南極海に固有である。
南極からは7種が知られており[30]、チサノエッサ属の Thysanoessa macrura、オキアミ属の6種が知られる。ナンキョクオキアミは一般に水深100mに生息し[31]、コオリオキアミは通常水深300-600m、最大4,000mに生息する[32]。大群で日周鉛直移動を行い、音響測定によると水深400mまで移動することが分かっている[33]。ナンキョクオキアミとコオリオキアミはともに南緯55度線以南に分布し、コオリオキアミは南緯74度線以南で優占しており[34]、流氷域にも分布する。その他にも Euphausia frigida、Euphausia longirostris、Euphausia triacantha、Euphausia vallentini などの種が南極海に分布する[35]。
形態
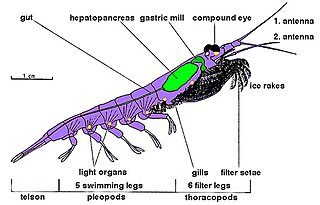

他の甲殻類と同様に、キチン質から成る外骨格を持つ。外見的には遊泳生のエビ類によく似ており、頭胸部は背甲に覆われ、腹部は6節からなる腹節と尾節からなる。腹部には10本の遊泳脚と尾扇がある。胸部には8節があり、それぞれに附属肢があるが、エビを含む十脚類ではその前3対が顎脚となっているのに対して、オキアミ類ではそのような変形が見られない。第2,第3節が鋏脚として発達する例や、最後の1-2対が退化する例もある。それらの胸部附属肢の基部の節には外に向けて発達した樹枝状の鰓がある。これが背甲に覆われないのもエビ類との違いである。よく似たアミ目とは胸脚の基部に鰓がないこと、尾肢に平衡胞がある点などで区別される。分類上はアミ目はフクロエビ上目とされ、系統的にもやや遠いと考えられている。2本の触角と、数対の胸脚を持つ。胸脚の数は属や種によって異なる。胸脚には摂食の為の脚と、体の手入れのための脚が含まれる。十脚目と共通して遊泳脚を持っており、これはロブスターやザリガニのものと類似している。このためオキアミは十脚目の姉妹群と考えられることがある。
外殻はほとんどの種で透明である。複雑な複眼を持ち、一部の種は色素を遮蔽することでさまざまな照度に適応している[36]。ほとんどのオキアミは成体でも約1-2cmで、いくつかの種は6-15cmに成長する。最大種である Thysanopoda cornuta は外洋の深海に生息する[37]。外部から見える鰓によって、他の甲殻類と簡単に区別できる[38]。
ソコオキアミは発光しないが、オキアミ科は発光器を持ち、生物発光を行う。ルシフェリンがルシフェラーゼによって活性化され、酵素を触媒とした化学発光が起こる。研究によると多くのオキアミのルシフェリンは、渦鞭毛藻のルシフェリンに似ているが異なる蛍光テトラピロールであり[39]、オキアミはおそらくこの物質を渦鞭毛藻を含む食事から獲得している[40]。オキアミの発光器はレンズと焦点を合わせる能力を備えた複雑な器官であり、筋肉によって回転させることができる[41]。これらの器官の正確な機能は未だ不明だが、繁殖など他個体との相互作用、方向感覚の調節、カウンターシェーディングなどの機能が考えられる[42][43]。
生態系内の役割
要約
視点
生物ポンプ

オキアミは生物ポンプによる海洋隔離の一端を担っており、まず植物プランクトンが大気から海洋表層に溶解した二酸化炭素(90 Gt yr−1)を一時生産の過程で粒子状有機炭素(~ 50 Gt C yr−1)に変換する。その後植物プランクトンはオキアミや動物プランクトンに消費され、それらもさらに高次の捕食者によって消費される。残った植物プランクトンは凝集体を形成し、動物プランクトンの糞とともに急速に沈み、混合層から排出される(< 12 Gt C yr−1 14)。オキアミ、動物プランクトン、微生物は表層の植物プランクトンや深層の堆積粒子を消費し、呼吸によって有機炭素を溶存無機炭素である二酸化炭素に変換するため、表層で生成された炭素のうち、1000m以上の深海へ沈むものはごくわずかである。オキアミや小型の動物プランクトンは摂餌や排泄によって粒子を小さく断片化し、粒子状有機炭素の排出を遅らせる。これにより溶存有機炭素が細胞から直接、またはバクテリアの可溶化を介して間接的に放出される。その後細菌は溶存有機炭素を溶存無機炭素に再ミネラル化する。日周鉛直移動をするオキアミ、小型動物プランクトン、魚類は夜間に表層の溶存有機炭素を消費し、昼間に中深層で代謝することで、炭素を深層まで能動的に輸送する。能動輸送は生物の生態に応じて季節的に発生する可能性もある[44]。
食性
多くのオキアミは濾過摂食を行う[26]。胸脚には細かい櫛があり、水を吸い込んで餌を濾過することができる。植物プランクトン、特に珪藻を餌とする種では非常に細かい。ほとんどが雑食性であるが[45]、少数の種は肉食性で、動物プランクトンや仔魚を捕食する[46]。食物連鎖の重要な要素であり、一次生産者である微細藻類を大型動物が食べられる形に変換している。Northern krillや他のいくつかの種は濾過器が比較的小さく、カイアシ類や大型の動物プランクトンを積極的に捕食する[46]。直径5mm以下のマイクロプラスチックを消化し、分解して環境中に排出することができる[47]。
天敵
魚やペンギンのような小型動物からアザラシやヒゲクジラのような大型動物まで、多くの動物がオキアミを捕食する[48]。生態系の撹乱によりオキアミの個体数が減少すると、広範囲に影響を及ぼす可能性がある。例えば1998年にベーリング海で円石藻が大量発生した際[49]、珪藻の濃度が低下した。オキアミは小さな円石藻を食べることができないため、特にツノナシオキアミの個体数が急激に減少した。これにより他の種にも影響を及ぼし、ミズナギドリの個体数が減少した。オキアミの減少はそのシーズンにサケが産卵しなかった理由の1つであると考えられている[50]。
寄生性の繊毛虫である Collinia 属はオキアミに感染し、感染した個体群を壊滅させる可能性がある。感染はベーリング海のトゲホクヨウオキアミや、北米太平洋岸沖のツノナシオキアミ、Thysanoessa spinifera、ノコギリテナガオキアミから報告されている[51][52]。アミヤドリムシ科に寄生されることもある。Oculophryxus bicaulis は Stylocheiron affine や Stylocheiron longicorne の眼柄に付着し、頭部から血を吸うことが判明している。寄生されたオキアミは成熟しなかったことから、宿主の繁殖を阻害していると考えられる[53]。気候変動もオキアミの個体群にとって脅威となっている[54]。
生態と行動
要約
視点

オキアミの生態は種によって若干の違いはあるものの、比較的よく理解されている[16][26]。孵化した幼生は三対の附属肢を持つノープリウスであり、その後ほぼ体全体が背甲に覆われるメタノープリウス期、腹部が伸長したカリプトピス期、複眼が柄を持って突き出すフルシリア期を経て、附属肢が発達した成体となる。生息域によっても異なるが、成熟までに1-3年を要すると考えられている。卵嚢内に卵を産む種では、ノープリウスとメタノープリウスの間にpseudometanaupliusという独自の期間がある。成長と脱皮を繰り返し、小型個体は脱皮の頻度が高い。体内に蓄えられた卵黄により、メタノープリウス幼生は栄養を得る。
カリプトピス期までに細胞分化が進み、口と消化管が発達し、植物プランクトンを食べ始める。その頃には卵黄が尽き、藻類の多い海洋表層に到達する。フルシリア期には最前部の節から遊泳脚を持つ節が生まれる。新しい遊泳脚は、次の脱皮時にのみ機能する。フルシリア期に追加される節の数は、環境条件に応じて同種であっても異なる場合がある[55]。フルシリア期を経て成体と同様の形となり、生殖腺が発達して性成熟する[56]。高緯度に生息するナンキョクオキアミのように6年以上生きるものもあれば、中緯度に生息するツノナシオキアミのように2年しか生きない種もある[8]。低緯度に生息する種の寿命はさらに短く、Nyctiphanes simplex の寿命は通常6-8ヶ月である[57]。
繁殖

繁殖期は種や気候によって異なり、一般に雄は雌の第6胸脚の基部にある生殖孔に精莢を産み付ける。侵入した精子は一時的に貯精嚢に蓄えられる。雌は卵巣に数千個の卵子を持ち、その量は体重の3分の1にもなる[58]。1回の繁殖期の間に複数回の繁殖を行うこともあり、その間隔は数日程度である[27][59]。
2種類の産卵方法が知られている[27]。ソコオキアミ、オキアミ属、Meganyctiphanes 属、チサノエッサ属、チサノポーダ属の57種は「broadcast spawners (放出産卵)」であり、雌が受精卵を水中に放出し、卵は通常沈んで分散する。これらの種は通常ノープリウス期で孵化するが、メタノープリウス期やカリプトピス期で孵化する例も発見されている[60]。残りの29種は「sac spawners (嚢産卵)」であり、雌が卵を胸脚の一部が広がった抱卵肢に付着させてメタノープリウス期に孵化するまで運ぶが、Hansarsia difficilis などの一部の種はノープリウス期またはpseudometanauplius期に孵化することもある[61]。
脱皮
外骨格よりも大きく成長し、窮屈になると脱皮する。若い個体は成長が早く、大型個体よりも頻繁に脱皮する。脱皮の頻度は種によって大きく異なり、同じ種の中でも緯度、水温、餌の入手可能性など多くの外的要因の影響を受ける。亜熱帯の種である Nyctiphanes simplex は、脱皮間隔が2-7日である。幼生は平均4日ごとに脱皮し、幼体と成体は平均6日ごとに脱皮する。南極海に生息するナンキョクオキアミでは、脱皮間隔は-1から4℃の水温に応じて9-28日であることが観察されており、北海に生息する Meganyctiphanes norvegica でも脱皮間隔は9-28日であるが、水温は2.5-15℃である[62]。ナンキョクオキアミは餌が足りないときには体の大きさを小さくすることができ、外骨格が大きくなりすぎると脱皮する[63]。同様の能力は、極地から温帯にかけての太平洋に生息するツノナシオキアミでも、高水温への適応として観察されている。他の温帯のオキアミにも同様の能力があると予測されている[64]。
群れ

ほとんどのオキアミは群れを作るが、その大きさと密度は種と地域によって異なる。ナンキョクオキアミの場合、群れの密度は1m3あたり10,000-60,000匹に達する[65][66]。群れを作ることは防御になり、小型の捕食者を混乱させる。2012年に発表された研究では、オキアミの群れの行動がモデル化され。他の個体の存在によって引き起こされる動き、摂餌、ランダムな移動が考慮された[67]。群れが密集すると、特に水面近くでは魚、鳥、哺乳類の捕食者の間で餌を巡る激しい争いを引き起こす可能性がある。群れは襲撃されると散り散りになり、中には瞬時に脱皮し、殻を囮にする個体も観察されている[68]。
移動

日中は深海で過ごし、夜間に水面に浮上する日周鉛直移動を行う。深く潜るほど活動は鈍くなるが[69]、捕食者との遭遇を減らし、エネルギーを節約することができる。オキアミの遊泳活動は胃の満腹度によって変化する。水面で餌を食べた満腹のオキアミは泳ぎが鈍くなり、混合層の下に沈んでいく[70]。沈む際には排泄物を出すため、これが南極の炭素循環に関与している。胃が空のオキアミはより活発に泳ぐため、水面に向かう。垂直移動は1日に2-3回起こることがある。ナンキョクオキアミ、ツノナシオキアミ、Euphausia hanseni、カクエリオキアミ、Thysanoessa spinifera など一部の種は、捕食される危険が高いにもかかわらず、摂餌と繁殖の目的で日中に水面に群れを形成する[71]。アルテミアをモデルにした実験では、オキアミが集団で垂直移動することにより下向きの水流を作り出し、海洋の混合に大きな影響を与える可能性があることが示された[72]。
毎秒5-10cmの速度で泳ぎ[73]、推進力として遊泳脚を使用する。より長い距離を移動すると海流の影響を受ける。脅威を感じると尾を振り回して比較的素早く水中を後進し、遊泳の10-27倍の速度に達する。ナンキョクオキアミのような大型種の場合、約0.8m/sに相当する[74]。オキアミの遊泳能力から、多くの研究者は成体のオキアミを弱い流れに逆らって移動するネクトンに分類している。幼生は一般にプランクトンとされる[75]。
海洋循環における影響
要約
視点
ナンキョクオキアミは生物地球化学的循環と[44][76]と南極の食物連鎖[77][78]において重要な種で、栄養素を循環させ、ペンギンやヒゲクジラ、シロナガスクジラに餌を供給する。
生物地球科学的循環における役割

オキアミは表層で植物プランクトンを食べ(図の①)、その一部が植物分解物の集合体として沈む(図の②)。これは簡単に分解されるため、水温躍層よりも下に沈まない可能性がある。オキアミは糞も放出し(図の③)、これは深海に沈むこともあるが、通常は沈む途中でオキアミ、バクテリア、動物プランクトンによって消費され、分解される(図の④)。氷縁域では糞がより深いところまで達することがある(図の⑤)。オキアミの脱皮殻は沈んで炭素フラックスに寄与する(図の⑥)。鉄やアンモニウムなどの栄養素は、オキアミの摂餌や排泄に伴って放出される(図の⑦)。これが表層近くで放出されると、植物プランクトンの生成を刺激し、大気中の二酸化炭素のさらなる減少につながる可能性がある。成体のオキアミの中には、より深いところに生息し、深海にある有機物を食べるものもいる(図の⑧)。水温躍層の下に有機物または二酸化炭素の形で沈んだ炭素は、季節的な混合の影響を受けなくなり、少なくとも1年間は深海に貯蔵される(図の⑨)。成体のオキアミの回遊により、深海の栄養豊富な水が混合され(図の⑩)、一次生産がさらに刺激される。また成体のオキアミは海底で餌を探し、呼吸によって二酸化炭素を深海に放出し、底生捕食者に消費される可能性がある(図の⑪)。南極海の海氷の下に生息する幼生は、広範囲にわたる日中鉛直移動を行い(図の⑫)、水温躍層の下に二酸化炭素を移動させる可能性がある。ヒゲクジラを含む多くの捕食者に消費されるため(図の⑬)、オキアミの炭素の一部はクジラが死んで海底に沈み、深海生物に消費されるまでの数十年間、バイオマスとして貯蔵される[44]。
個体レベルの栄養素の循環

オキアミは脱皮時に、溶解したカルシウム、フッ化物、リンを外骨格から放出する(図の①)。外骨格を形成するキチンは有機物であり、深海の沈降粒子フラックスに寄与する。オキアミは植物プランクトンや他の動物を消費して得たエネルギーの一部を呼吸によって二酸化炭素に変換する(図の②)。中深層から大群で水面まで泳ぐとき(図の③)、栄養分の少ない表層水に栄養をもたらす可能性があり、アンモニウムとリン酸が鰓から放出され、排泄の際には溶解した有機炭素、窒素、尿素、リン(DOC、DON、DOP)が放出される(図の②および④)。粒子状の有機炭素、窒素、リン(POC、PON、POP)と鉄を含む沈みやすい糞を放出する。鉄はDOC、DON、DOP とともに周囲の水に浸出すると生体利用が可能になる(図の⑤)[44]。
人との関わり
要約
視点
漁業の歴史

オキアミは少なくとも19世紀から人間や家畜の食料として採取されてきたが、日本ではおそらくそれ以前から知られていた。大規模な漁業は1960年代後半から1970年代前半にかけて発展し、現在は南極海と日本近海でのみ行われている。歴史的にオキアミ漁業が盛んな国は日本とソ連、ソ連崩壊後はロシアとウクライナであった[79]。漁獲量がピークを迎えた1983年には南極海だけで約52万8千トン(うちソ連が93%を漁獲)が漁獲され、現在は乱獲防止のために管理されている[80]。1993年、ロシアがオキアミ漁業から撤退したことと、南極の海洋生物資源の保存に関する委員会がナンキョクオキアミの持続可能な利用のために最大漁獲量を定めたことにより、オキアミ漁業は衰退した。2011年10月の見直しの後、委員会は漁獲量を変更しないことを決定した[81]。南極での年間漁獲量は10万トン前後で安定しており、これは委員会の漁獲割当量のおよそ50分の1に相当する[82]。おそらくコストの高さと政治的および法的問題により、漁獲量は制限されている[83]。日本の漁業は約7万トンで飽和状態になった[84]。オキアミは世界中に生息しているが、南極海では個体数が豊富で漁獲しやすいため、操業が好まれている。南極海のオキアミは「クリーンな製品」とみなされている[79]。2018年には、南極で操業しているほぼ全てのオキアミ漁会社が、ペンギンの繁殖コロニー周辺を含む南極半島周辺の広大な海域での操業を2020年から中止すると発表した[85]。
消費

ナンキョクオキアミの総バイオマス量は4億トンにも達するが、このキーストーン種に対する人間の影響は増大しており、2010年から2014年にかけて総漁獲量は39%増加して294,000トンとなった。オキアミの漁獲を行う主な国は、ノルウェー(2014年の総漁獲量の56%)、韓国(19%)、中国(18%)である[82]。
漁獲されたオキアミは未加工もしくはフリーズドライ加工され、または粉末状で販売され、養殖漁業の飼料用、釣り餌、観賞魚の餌などに利用される。飼料としてのオキアミには、魚の耐病性向上や、観賞魚の体色の発色向上などの効果があって人気が高い。日本ではナンキョクオキアミの34%、ツノナシオキアミの50%が魚の飼料として消費される。また日本では70年代に海釣りの撒きえさとして導入され、黒鯛やメジナやその他海水淡水魚、またサビキ釣りのテクニックに革命を起こした。ナンキョクオキアミの4分の1、ツノナシオキアミの半分は釣りえさ用である。オキアミはタンパク質とω-3脂肪酸を豊富に含んでおり、21世紀初頭からは人間の食料、オイルカプセルなどのサプリメント、家畜の餌、ペットフードとして開発が進められている[79][81][86]。
魚肉ソーセージなど加工食品の原料にもなり[87]、また調味料として塩辛も作られている。これは朝鮮半島や日本でキムチの発酵にアキアミの塩辛同様に使われる事がある[88]。以前は漁獲後の劣化が早く風味落ちがするため、人間の食用としての消費はきわめて少なかったが、近年加工技術の進化により、ツノナシオキアミはサクラエビの安価な代用品としてお好み焼きなどに利用されている。オキアミは塩辛く、エビよりも魚の風味がやや強い。市販の製品として大量に消費するためには、食べられない殻を剥く必要がある[86]。釣りえさ用として販売されているオキアミの食用は、控えるべきである。原料鮮度や製造過程の衛生管理が食品加工法規の適用外であり、また食品に適さない薬品が添加されている可能性もあるからである。
DHA・EPA・アスタキサンチンの摂取を目的に南極オキアミから採取した油脂クリルオイルを原料として製造される健康食品もある。2011年、アメリカ食品医薬品局は、製造されたクリルオイル製品が人間の消費に安全であると発表した[89]。
オキアミを含む小型甲殻類は東南アジアで最も広く消費されており、殻付きのまま発酵させ、細かく挽いてシュリンプペーストを作ることが多い。炒めて白米と一緒に食べたり、様々な伝統料理にうま味を加えるために使用したりする[90][91]。発酵過程で得られる液体は魚醤としても使用される[92]。カップヌードルの具材に使われるエビがオキアミであるとされることがあるが、使用されているのはプーバランである。
食料以外での利用
オキアミは中程度のレイノルズ数の領域で機敏に泳ぐが、この領域では無人水中ロボットの移動が難しく、オキアミの移動を研究することで、水中ロボットの設計に応用する試みが進められている[93]。
出典
参考文献
外部リンク
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
